薬剤師国家試験に合格し晴れて病院薬剤師として働き始めると、「どの本で勉強すれば良いのだろう」と思いますよね。
私も病院薬剤師として働き始めてから勉強しよう!と考えた時にどの本がおすすめなのか分からず、本屋さんに何時間もいた覚えがあります。
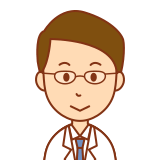
薬剤師向けの本はたくさん種類があるから選ぶのが大変!
せっかく薬剤師向けの本を買うならば、少しでも多くの知識を身に付けられる良い本を選びたいですよね。
そこで私が実際に買って読んだ本の中で新人病院薬剤師のみなさんにおすすめしたい本をご紹介します。
もちろん新人病院薬剤師だけではなくブランクのあるママ薬剤師にもおすすめしたい本ですよ!
この記事を読み終わる頃、あなたにとって最適な本を選ぶことができるでしょう。
<この記事を書いた人>
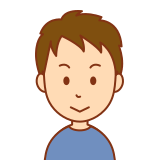
新卒から国立大学病院薬剤師として勤務していた山村ゆちです
- 薬剤師歴:2022年現在、7年目
- 都内私立大学薬学部→新卒で国立大学病院薬剤師として勤務
- 現在1児の母として子育てに奮闘中
病院薬剤師のことならお任せください!
病院薬剤師のおすすめ本!基礎を学べる参考書8選!
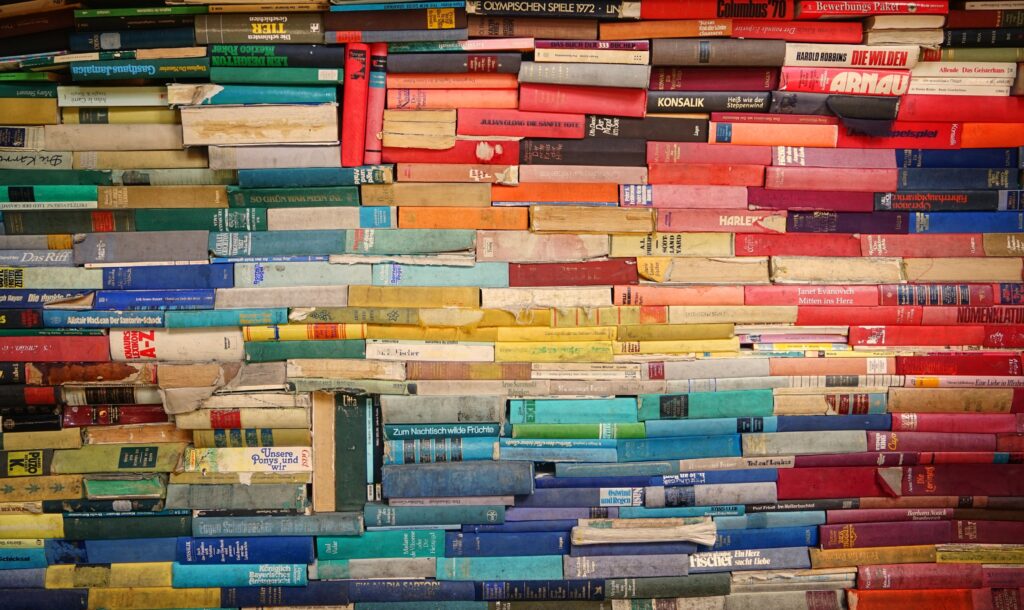
まずはじめに病院薬剤師として働き始めてすぐに必要になる本のおすすめを一覧でご紹介します。
- 薬がみえる
- 薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100
- 同種・同効薬の使い分け
- 薬効別 服薬指導マニュアル 第9版
- 薬局で使える実践薬学
- 処方がわかる医療薬理学
- 薬トレ 薬剤師の臨床センスを磨くトレーニングブック
- 薬剤師レジデントマニュアル
これらのおすすめ本はどれも有名で、他のサイトにも載っているものばかりです。
「薬局」と名前が付いている本もありますが病院薬剤師が読んでも勉強になる本ばかりですので1つずつご紹介していきますね。
薬がみえるシリーズは全薬剤師におすすめしたい本
薬がみえるシリーズは2022年4月現在、4冊に分かれて出版されています。
- 薬がみえる vol.1は神経系、循環器系、腎・泌尿器系、漢方薬
- 薬がみえる vol.2は糖脂質代謝、産婦人科系、血液系、アレルギー系、眼、耳鼻、皮膚系
- 薬がみえる vol.3は消化器系、呼吸器系、感染症、悪性腫瘍
- 薬がみえる vol.4は薬力学、薬物動態、製剤学
薬が見えるシリーズは病態と治療薬が同じページにまとまっているため、薬が臨床現場でどのように使われているのかがパッとわかります。
また、全てのページがカラーであり図も豊富に載っているため、薬剤師だけではなく医師や看護師など全医療従事者におすすめしたい本です。
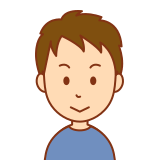
私も薬剤師になってまずはじめに薬がみえるを買ったよ。
新人薬剤師だけではなく、ベテラン薬剤師でも「あれ?この薬の作用機序ってなんだっけ?」と思う時にパッと調べられるので1冊は持っていると便利です。
薬がみえるvol.4は2020年に発売された本で、薬物動態学や薬力学、製剤学など薬剤師が1番力を発揮できる分野について詳しく説明が書いてあります。
薬が見えるシリーズを買って読むと臨床現場で役立つ薬剤師への一歩を踏み出せますよ♪
薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100はバイブル
同じ作用機序を持つ薬の使い分けは医師から聞かれることが多いので、パッと答えられたらカッコいですよね。
「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100」は薬局薬剤師だけではなく病院薬剤師にも役に立つ参考書です。
例えば抗アレルギー薬だとそれぞれの薬の特徴や違いについて参考文献付きで詳しく書いてあります。
病院薬剤師には同じ作用機序を持つ薬、いわゆる同種同効薬について医師から問い合わせを受けるため必ず勉強する必要があります。
読みやすい文章で書かれているため、同種同効薬について勉強するためにおすすめな本ですよ。
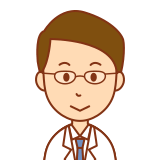
こぼれ話がところどころにあるから肩の力を抜いて読み進められるよ。
同種同効薬の使い分けは全薬剤師に必須!
「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100」を読んだ後にもっと詳しく同種同効薬について勉強したいあなたにおすすめの1冊が「同種・同効薬の使い分け」です。
月刊薬事の2021年5月臨時増刊号として発売されており、336ページととてもボリュームのある充実した本です。
この本は循環器系、呼吸器系、内分泌・免疫系、消化器系、精神・神経系、感染症の6章に分かれて詳しく解説しています。
私は薬剤師1年目の時に同種同効薬について勉強したことで、薬について勉強するのが楽しい!と感じるようになりました。
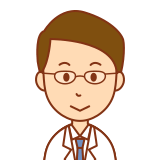
同種同効薬をどれだけ提案できるかが医師との信頼を築けるかに掛かっていると思うよ。
「同種・同効薬の使い分け」を使って勉強して、周りの薬剤師と差を付けましょう!
薬効別服薬指導マニュアルは服薬指導を行う薬剤師は必見!
服薬指導をしていると「あれ、この薬ってどんな副作用があるんだっけ?」と思うことがありますよね。
いつも見慣れない薬について患者に説明するためにパっと副作用や注意点について確認したい時、「薬効別服薬指導マニュアル」はあなたを助けてくれます。
「薬効別服薬指導マニュアル」は勉強に使っても良し、辞書としても使ってよし、2つの使い方ができます♪
私は病棟薬剤師として毎日服薬指導をしていた時、「薬効別服薬指導マニュアル」を常に机の上に置いて辞書として使っていました。
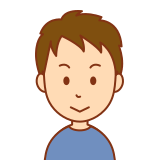
パっと調べられるから辞書代わりに1冊持っていると安心だよ。
病棟で服薬指導を行う病院薬剤師ならば1冊持っていても良いでしょう!
薬局で使える実践薬学は病院薬剤師にもおすすめ!
「薬局で使える実践薬学」はタイトルに薬局と書いてありますが病院薬剤師にもおすすめの本です。
大学で学んだ薬物動態学の知識を使って日常業務での疑問点を解説しているので、新人の病院薬剤師にとって勉強しやすい本の1つです。
新人だけではなく、ブランク明けのママ薬剤師、もう1度薬物動態から勉強したい薬剤師にもおすすめです♪
処方がわかる医療薬理学は辞書として使うための本
「処方がわかる医療薬理学」は病態と薬について1冊にまとまっている本です。
先ほどご紹介した薬がみえるシリーズは4冊に分かれているため持ち運びに不便ですよね。
薬がみえるシリーズを読み終えた後、もう少し詳しく病態から薬の使い方について勉強したい薬剤師におすすめです。
2年ごとに出版されている本なので常にほぼ最新の情報で勉強できるのは嬉しいですよね♪
全392ページとボリュームたっぷりな「処方がわかる医療薬理学」で勉強することで、周りの薬剤師と差がつけられますよ!
薬トレ薬剤師の臨床センスを磨くトレーニングブックは症例から学ぶ
薬トレ薬剤師の臨床センスを磨くトレーニングブックは読み物ではなく症例検討をしながら学習する本です。
イメージとしては薬剤師国家試験の実践問題のような形式で、1つの症例に検査値や薬について問題が出題されています。
解説も書いてあるのですが、あまり親切ではないため自分で治療のガイドラインや検査値について調べる必要があります。
自分で治療のガイドラインを調べたり薬について調べたりする過程で自分自身の力が知らないうちに付く本です。
1冊で260症例も収録されているため、1冊終える頃には薬剤師としての力がメキメキ上がっていること間違いなしですよ♪
薬剤師レジデントマニュアルは病院薬剤師の基礎が充実
薬剤師レジデントマニュアルはレジデントだけではなく病院薬剤師として働き始める薬剤師のみなさんにおすすめです。
薬剤師として知っておくべき基本的なことが丁寧に書いてあるのでブランク明けのママ薬剤師にもおすすめの1冊。
白衣のポケットに入れておくと気になった時にすぐに調べられて良いですよ♬
私は薬剤師レジデントマニュアルを読んで病棟業務の基礎について勉強しました。
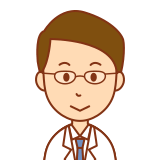
薬剤師レジデントマニュアルは本当に基礎から病棟業務を学べるよ。
病院薬剤師の基礎を勉強するため、薬剤師レジデントマニュアルは非常におすすめの1冊です。
病院薬剤師のおすすめ本!領域や目的別の参考書7選!
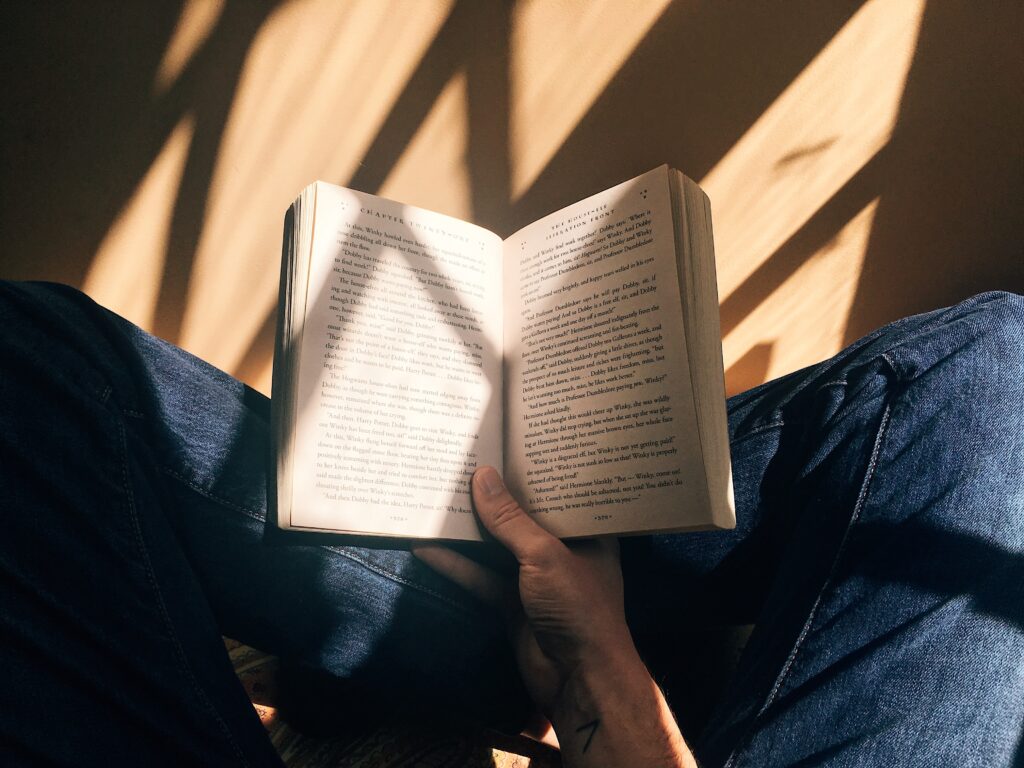
薬剤師業務について基礎的なことを勉強した後には少し専門的な勉強をしたくなるでしょう。
そこで次は専門別におすすめの勉強本について説明しますので、まずは一覧表をご紹介しますね。
- 感染症プラチナマニュアル
- 抗菌薬の考え方、使い方
- レジデントのためのこれだけ輸液
- ICU/CCUの薬の考え方、使い方
- OTC医薬品の比較と使い分け
- これからの薬物相互作用マネジメント 臨床を変えるPISCSの基本と実践
- 3ステップで推論する副作用のみかた・考え方
もしかしたら既にあなたが持っている勉強本も載っているかもしれません。
それでは各参考書のおすすめポイントや特徴について1つずつ説明していきます。
感染症プラチナマニュアルは多くの視点から学べる
感染症プラチナマニュアルはポケットサイズの本なので白衣のポケットに入れて必要な時に取り出して抗菌薬や感染症について確認ができます。
特徴はそれぞれの抗菌薬についての解説や感染症についての解説がしっかりまとまっている点です。
感染症プラチナマニュアルは抗菌薬からのアプローチだけではなく、微生物や疾患からのアプローチもあるため多くの視点から抗菌薬について学べます。
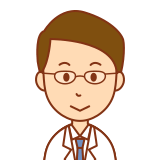
臨床現場では薬剤師だけでなく医師も読んでいる本だよ。
感染症について勉強したい場合にまず始めに読む本としておすすめしたい1冊です。
抗菌薬の考え方使い方は薬の選択方法について学べる
抗菌薬の考え方、使い方は医師の岩田健太郎先生が執筆した医師向けの抗菌薬の参考書で、抗菌薬の選択方法について学習ができます。
医師向けではありますが病院薬剤師が読むことで医師の処方意図が勉強できます。
業務内で医師と抗菌薬についてディスカッションするためにも病院薬剤師が読んでおくと医師とスムーズに連携できるでしょう。
レジデントのためのこれだけ輸液は基礎から学べる
レジデントのためのこれだけ輸液は点滴の基礎からしっかり学べる本です。
輸液は点滴療法の基本なので、生理食塩水や5%ブドウ糖液について薬剤師もしっかりと理解しておく必要があります。
研修医向けに書かれた本ですが病院薬剤師にも非常にわかりやすく書かれているためおすすめです。
病院薬剤師が輸液の基本について学習するにはこの1冊で十分ですよ♪
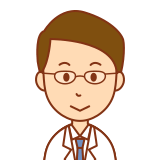
輸液について基本的なことから勉強したい薬剤師にはおすすめ!
ICUの薬の考え方使い方は集中治療部配属にはマスト!
ICUの薬の考え方使い方はICUを始めとした集中治療部に配属された薬剤師のバイブルです。
ICUで使う薬は鎮痛薬、鎮静薬、降圧薬、循環作動薬など一般病棟で使われる薬とは少し種類が異なりますよね。
ノルアドレナリンやドブタミンなど使い方が特殊な薬はICU担当の病院薬剤師にとって知っておきたい知識です。
実際に私もこの本を使って勉強したことでICU病棟での業務がスムーズになりました。
この本で勉強することでICU病棟の病院薬剤師としての知識をどんどん吸収していけること間違いなしです!
OTC医薬品の比較と使い分けは病院薬剤師も必要!
OTC医薬品の比較と使い分けは薬の比較と使い分けは100と同じ児島悠史先生が書いた本です。
薬の使い分けと同じく読みやすい文体でサラサラと読み進めることができるため勉強がしやすい本の1つです。
OTC医薬品は病院薬剤師には関係がないように思いますが患者さんから聞かれることが意外と多いので、OTC医薬品についての知識も必要になります。
私も病棟で患者さんに服薬指導をしている時にOTC医薬品の違いなどの質問を受ける機会が多く、OTCについても勉強が必要だなと感じました。
OTCの知識をつけたい病院薬剤師にとてもおすすめな本ですよ♪
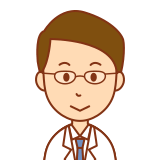
この本を片手にドラッグストアに行ったら学びが深まりそうだね。
これからの薬物相互作用マネジメント臨床を変えるPISCSの基本と実践
薬の相互作用を考える時、あなたはきっと添付文書の相互作用の部分を読んで検討すると思います。
しかし、全ての薬に対して相互作用が検討されているわけではないので、きっとあなたは薬の相互作用についての情報が足りない経験をしたことがあるでしょう。
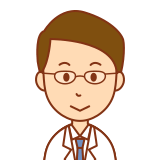
PISCSって何?
PISCS(ピクス)は薬物相互作用の強さと予測を臨床的なリスク評価設定に応用するためのフレームワークのことを言います。
PISCSが使えると自分自身で相互作用の見当がつけられるようになるため、薬剤師として医師や看護師から重宝される薬剤師になれます。
PISCSは難しい考え方のように感じますが、この本を読むことで簡単に理解することができます。
しっかりとPISCSを自分のモノにして、薬物治療に生かせるようにしましょう♪
3ステップで推論する副作用のみかた考え方は中級者向け
今までご紹介した本を読み込んだ上でこの本を読むと、副作用についての考え方について深く理解ができます。
副作用とひと言で言っても、薬の影響なのか、病気の影響なのか分かりづらいことがありますよね。
医師と副作用についてディスカッションをする時に、副作用のみかたや考え方のステップを知っておくとスムーズになります。
中級者向けの本ですが、長期休暇などに読み進めることで周りの薬剤師と差がつけられますよ。
病院薬剤師のおすすめ本をお得に買う2つの方法!
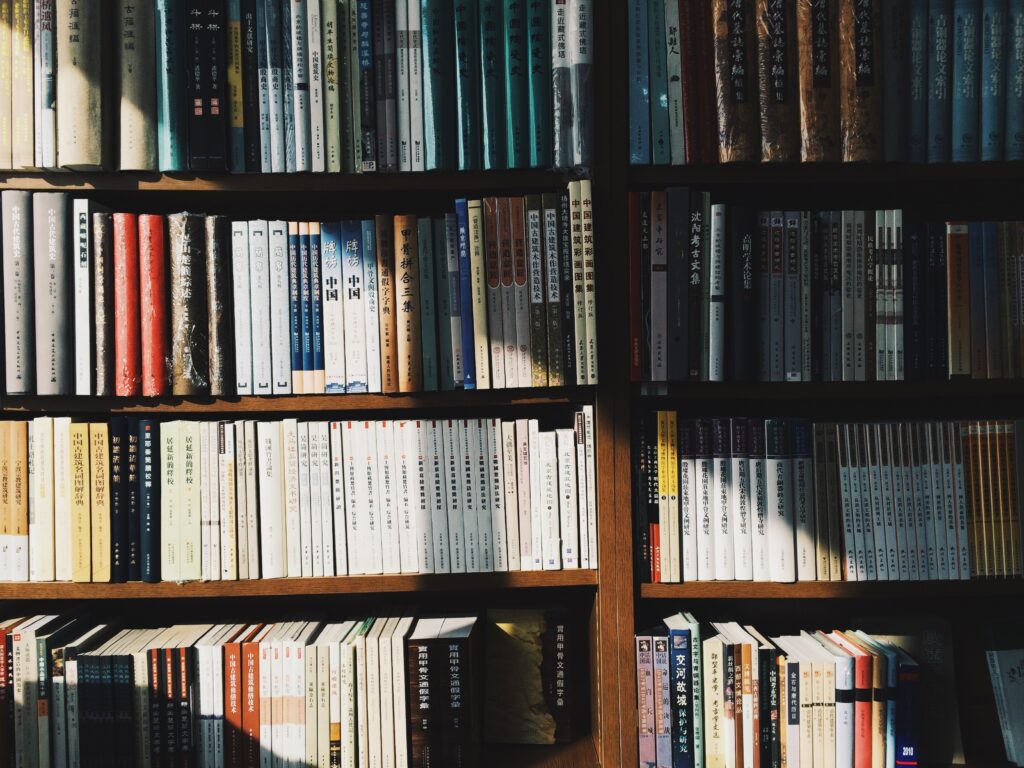
いざおすすめ本を買おうとしても、薬剤師向けの本は高価なものが多いので買うのをためらってしまいますよね。
私もいつも自分のお財布事情とにらめっこしながら本を買っていましたが、いつも少しでも安く本を買いたいなと思っていました。
そこで少しでも安く病院薬剤師のおすすめ本を買うためにあなたにおすすめしたいのが以下の2つの方法です。
- Amazonプライム会員に登録する
- m3に登録する
私も調べるまで知らなかったので「悔しいな~!!」と思っているくらいお安くおすすめ本を買えるため、1つずつ紹介していきます。
Amazonプライムに登録してお得におすすめ本を購入する
Amazonプライム会員に登録すると、送料無料や最大15%のポイント還元サービスが受けられます。
Amazonミュージックなど楽しめるコンテンツがたくさんあるため、Amazonプライム会員になることをおすすめします♪
m3に登録してアマゾンギフトをもらうことで本を購入する
m3(エムスリー)に新規登録することで、アマゾンギフトがもらえることを知っていますか。
m3は無料で登録ができる上、お役立ちコラムや薬剤師同士が交流できる掲示板があるため登録することをおすすめします♪
まとめ

- 病院薬剤師のおすすめしたい基礎を学べる本は以下の8つがある
- 薬がみえる
- 薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100
- 同種・同効薬の使い分け
- 薬効別 服薬指導マニュアル 第9版
- 薬局で使える実践薬学
- 処方がわかる医療薬理学
- 薬トレ 薬剤師の臨床センスを磨くトレーニングブック
- 薬剤師レジデントマニュアル
- 病院薬剤師のおすすめしたい領域や目的別の本は以下の7つがある
- 感染症プラチナマニュアル
- 抗菌薬の考え方、使い方
- レジデントのためのこれだけ輸液
- ICU/CCUの薬の考え方、使い方
- OTC医薬品の比較と使い分け
- これからの薬物相互作用マネジメント 臨床を変えるPISCSの基本と実践
- 3ステップで推論する副作用のみかた・考え方
- 病院薬剤師のおすすめ本をお得に買うためにはAmazonプライム会員、m3会員に登録することがおすすめ
病院薬剤師のあなたが学びたい参考書が見つかることを願っています。
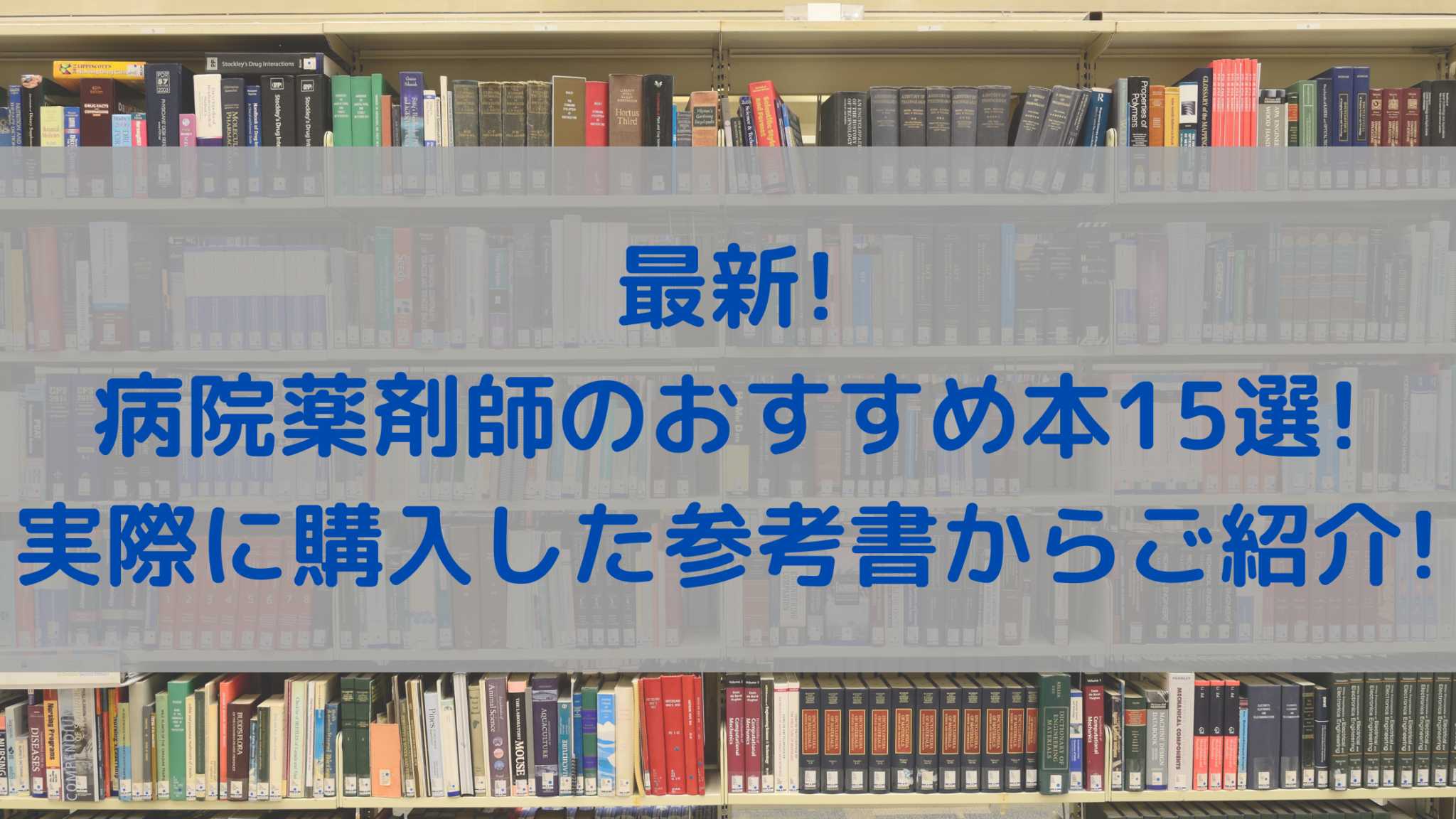













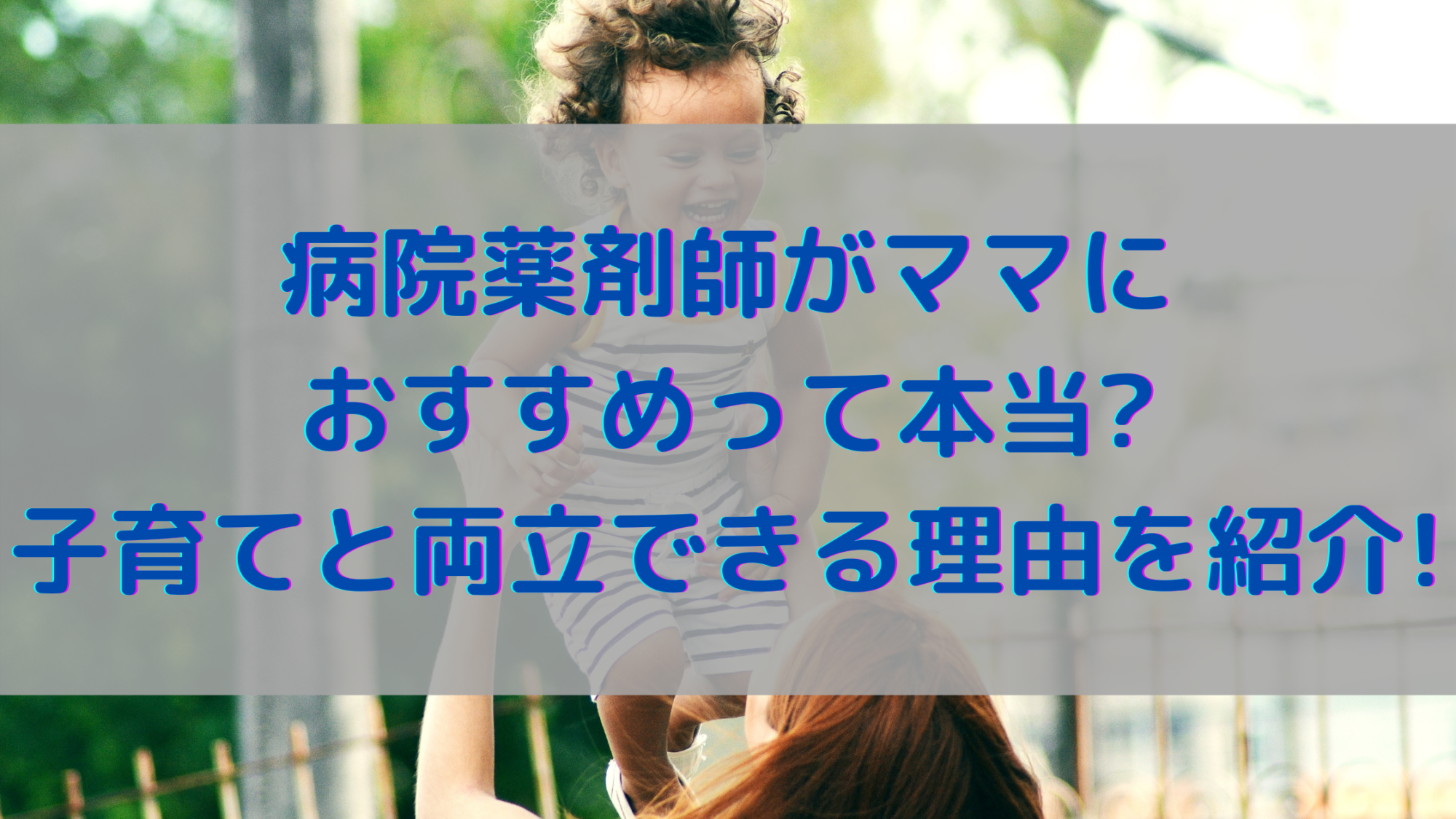
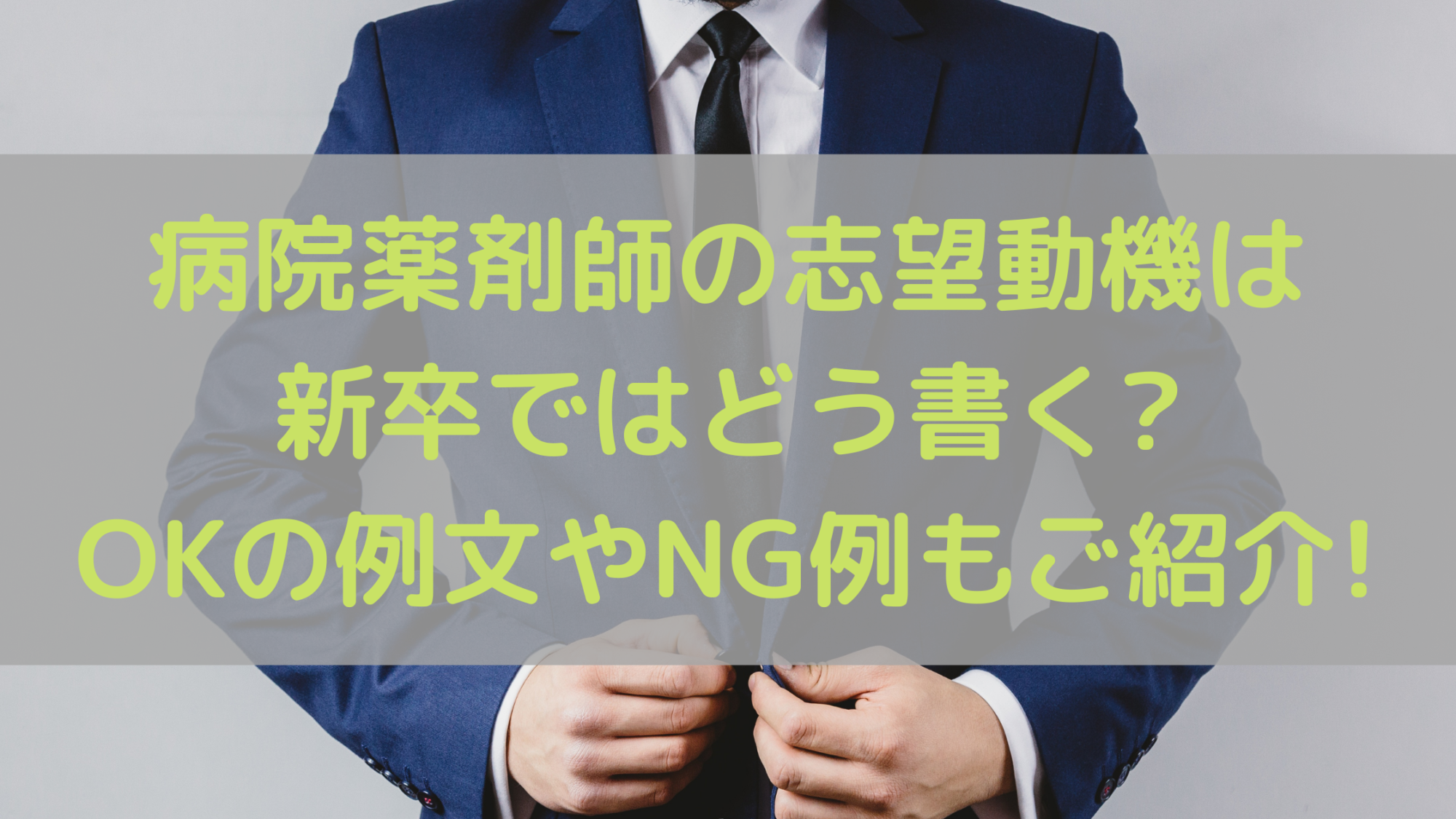
コメント